
欧州版にだけ入っている部分は、西浦さんにご提供いただきました。
翻訳していただける方、募集中!
エルネスト・アンセルメ(Ernest Ansermet 指揮者)

あれは1930年頃だったでしょうか。私はベルリンではじめてカール・シューリヒトと接する機会を得ました。その後、スヘベニンゲンの夏期コンサートを数年間交代で受け持ったことも
ありました。そして、ナチスが数々の術策を弄して彼に迫ったあの大戦中、私は彼がスイスに移り住むのに、手を貸すことができました。爾来、私達の友情は、日を経るにつれてますます深くなっていったのです。
私は、シューリヒトの素朴さ、明快さ、そしてその魅力的なしぐさを、いつもこよなく愛していました。そして、私達の交響曲のレパートリーの中の主だった作品を演奏するに際して、殆どいつもお互いの意見が完全に一致する大きな共感部分を持っていたのです。
私達のもとから去っていってしまったのは、偉大な古典的伝統の名残を私達に伝えてくれた、すぐれた
指揮者なのです。彼の想い出は、その演奏を聴いたことのあるすべての人の胸に、脈々と生き続けてゆくことでしょう。(音楽雑誌「フランセ・ムジカ」所載)
ヴァルター・アーベントロート(Walter Abendroth)
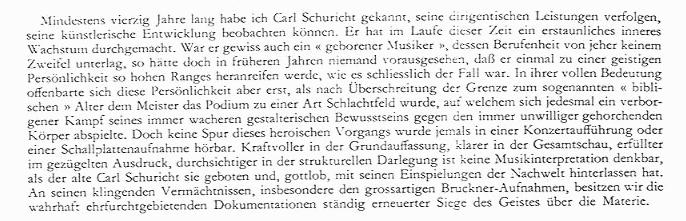
翻訳:小田謙爾氏
ゼルジュ・ボード(Serge Baudo 指揮者)
カール・シューリヒトの肉体が亡びてしまった今、私達は一人の偉大な音楽の指揮者を
失ったことになる。生前の彼を知る者は、すべて深い悲しみに沈んでいる。
彼の周囲には、卑俗なものは何一つとしてなかった:大げさな宣伝や、いわれのない悪評はなく、あるのはただ、本当に音楽を愛する人の持つ信頼だけであった。
私がパリ音楽院管弦楽団員だった頃、彼の指揮の下に何回か演奏を行う幸運に恵まれた。このことは
私の生涯を通じての大切な想い出として残ってゆくことだろう。
その音楽的にも人間的にも傑出した資質によって、彼は歴史に残る偉大な芸術家の一人としての位置を与えられたのである。
ボリス・ブラッハー(Boris Blacher 作曲家)
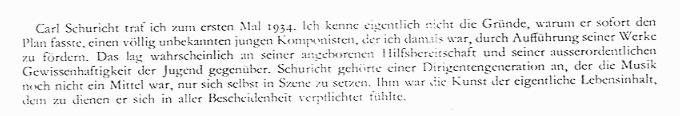
翻訳:山口 春樹氏
エリザベス・ブラッスール(合唱指揮者)
あらゆる意味での”長”であり、優れた人格者であるカール・シューリヒトに、私がはじめて会ったのは、1947年でした。彼と共にした仕事はどれも内容のある豊かなものでした。明快で情熱的、整然としていて抱擁力に富む彼の指揮は、他に類をみないものです。厳しいけれど、常に真実を伝える彼の指示には、私達は皆即座に従ったものです。
誰にでも愛され、敬われていたシューリヒト、彼の友人の一人であったことはすばらしい恵みだと思います。逝ってしまった彼の空席は、何物を以ってしても埋め尽くすことはできないのです。
ジョゼ・ブリュイル(Jose Bruyr)
<一人の人間を定義するのは危険な行為だ>と、ポール・ヴァレリーが何かに書いている。ましてや、
この定義を一言のもとに行なおうとするなど、破滅的な危険かもしれない。
だが、偉大なカール・シューリヒトのために私はあえてこの危険をおかし、勇を鼓してこれに立向おう。
―カール・シューリヒトは「意識」であった。既にその細部まで熟知している楽譜を、小節ごとにもう一度検討しなおしている彼の姿を、ドレル・ハンドマンがありありと描き出している。指揮者の世界に「完全」が存在する限り、誰でもこれだけの精進をすれば、その努力に見合うだけの完全さは得られたであろう。
驚異的なことは、カール・シューリヒトにおける完全さが、この精進を、はるかにしのぐ大きなものだったことだ。「完璧は冷たい」と云われる。《冷ややかな完璧》は、《優秀な巨匠》と同様、慣用語辞典にもみられる語句である。しかしカール・シューリヒトにあって、<完璧>は、熱情、抒情、そして清らかな激情の詩となってあらわれるのである。
ポール・クローデルによれば、<卓越した音楽、それは失楽園からの妙なる響であり、神の呼び声であり、想い出なのである。>
ギー・エリスマン(Guy Erismann)
<可能な限り遅く、しかも尚早すぎた死>私の持つカール・シューリヒトへの想い出は、選ばれた人にのみ捧げられるこの言葉にあてはまるものである。的確で厳しい観察力、純粋さを失わず、自己を簡単に普遍化してしまうことをきっぱりと拒否しながら、時代を凌駕してゆく力強い意志、控えめでありながら揺るぐことのない確信、理論よりも実際に基づく権威、これが、私の見たカール・シューリヒトの姿だった。ミュンヘンで、彼が最も愛したバイエルン放送交響楽団の指揮壇に立っていたときの。
偉大な指揮者の死とともに、断ち切られてしまうといわれる伝統の糸を、カール・シューリヒトが遠く我々の時代にまで延長してくれた。真の伝統とは、常に新しい現象を伴うものであり、それでなければ伝統とよぶに値しないものであろう。すなわち、伝統とは流動的なもの、あるいは、存在しないとさえいえるものなのだと思う。シューリヒトがこの考えを裏付けてくれている。常に若々しいロマンティシズムと、状況にふさわしくコントロールされた高揚を表現し、永遠にそして秘めやかに美と偉大さを見つめる心を抱かせることによって、現代の聴衆を満足させてくれるのである。
オーケストラの友人であり同僚として、繊細でしかもダイナミックに指揮壇に立つ彼、また時には、
譜面台に寄りかかりながら、動作でよりもむしろ視線で、的確に、そして自由に指示を与えている彼、
そんな彼の姿を、今もまのあたりに見るおもいがする。
ジャン・アモン
カール・シューリヒトは、ドイツ指揮者の中に流れる主潮を我々に伝える最後の一人であろう。
感覚の高貴さと内面性、オーケストラの構成とその均衡のすばらしい科学性、作品と聴衆に払う
尊敬の念にみられる叡智と深い洞察、思考の高さ、超俗性、、、。これらが逝いてしまったこの
偉大な長老の本質であり、演奏家としての気質と人間性の命数であろう。彼のレコードが、それを
立証してくれる。このレコードはまた彼にとっての神である<音楽>の前に、生涯をかけて謙虚で
しかも絶対的な下僕であったこの魅力溢れる男の精神と知性と心情を、ただ想い出させてくれるだけでなく、その死を超越して、我々がそれ等と直接語り合うことを可能にしているのである。
フリードリッヒ・ヘルツフェルト(Friedrich Herzfeld)
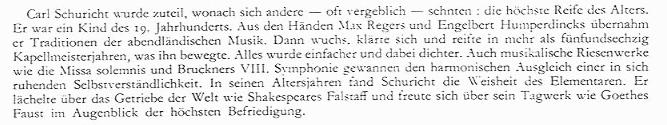
パウル・クレツキー(Paul Klecki 指揮者)

カール・シューリヒトを喪ったことにより、音楽の世界は莫大な損失を蒙ったことになる。それは単に優れたオーケストラ指揮者を失ったというだけにとどまらず、シンフォニーの文献から、偉大な傑作を、深く、また繊細に探求し、我々の前に紹介してくれた、まったく真摯な一人の音楽家を失ったことになるのである。
彼の数々の演奏会の思い出は、私にとって永久に忘れることのできないものとなるだろう。
ラファエル・クーベリック(Rafael Kubelik 指揮者)
カール・シューリヒトと共に、その音楽に対する献身が、常に私の賞賛の的となっていた、一人の
男が失われてしまった。それは演奏する作品の中に、自己のすべてを投入し、芸術の中に
真実と純粋さを求めることに生涯を捧げた、偉大な精神の一つなのであった。たくましい支柱にも似て、それなくしては芸術が生命を保つことができない高い理想を備えた、このような人間をこそ、世の中が必要としているのだ。
カール・シューリヒトは、死後も尚若い世代への規範として、永遠の命を保っている。
ダニエル・ルスュール(Naniel-Lesur 作曲家)
豊かな人間性と音楽性、明晰な頭脳、優しく、しかも勇壮であり、慎しみ深く風刺精神に富む賢さなどが輝く彼の視線。その中にカール・シューリヒトのすべてがあり、そしてそれこそが、彼の永遠の若さの証しでもあった。
演奏しようという作品に打ちこむ彼の情熱の烈しさは、私達を知らず知らずのうちに、そこへ導き、
彼を愛さずにはいられなくしてしまうのだった。
ロリン・マゼール(Lorin Maazel 指揮者)

巨匠シューリヒトの演奏を聴く時、私はいつも限りない喜びを感じ、その音楽に対する崇高な簡潔さには、いつも限りない賞賛をおくっていました。高度に洗練されたテクニックが、生来の音楽的直感と結びついて、彼の演奏には、ほとんど素朴ともみえるような心暖まる幅広さがありました。
シャンゼリゼ劇場の舞台裏で、ベートーヴェンの第9の練習を聴いた時のことでした。私は演奏開始時間に遅れて、誰が指揮をしているのかわからないままにその演奏に耳を傾けていましたが、すぐに「これこそ、この曲のあるべき姿をそのままに伝えている演奏だ」と思いました。幕のすき間から舞台をのぞき、はじめて指揮をしているのがカール・シューリヒトだということがわかったのです。
ユーディ・メニューイン(Yuhudi Menuhin ヴァイオリニスト、指揮者)

偉大で、尊敬にあたいするカール・シューリヒトと、その時代を共にする人々においてこそ、レコードの威力が、もっともその効果を発揮するのです。
なぜなら、音楽の音の一つ一つが、実際の人間の動作と結びついていた旧い時代、例えば質素な家から洩れてくるクラヴィーアのタッチがピアノに向う少女の姿に通じるというあの時代を正確に実感としてつかむには、私の齢が足りませんし、音楽史の上での革命である”レコード”が、私の精神にも心にも欠かせないものとなっているにも拘わらず、それが完全に私の中に根付き、定着するに至るには少々年齢をとりすぎているのです。
カール・シューリヒトと一緒にした仕事は、不幸にしてレコードには吹き込まれませんでした。
ただアスコナ放送局が録音したテープがあるだけです。だからこそ、このレコードアルバムが私にもたらす懐かしい想い出は、一層貴重なものなのです。
マリウス・モンニケンダム(Marius Monnikendam)
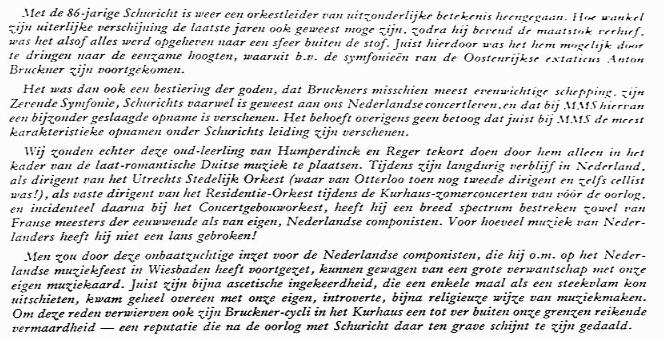
With the death of the 86-year old Schuricht, a orchestra conductor of exceptional impression passed away. His appearance was quite unstable over the last few years and if he rose the baton, almost all was rised to an atmosphere higher than the original surrounding. Therefore he was at extreme heights. This reuslted in the symphonies of Anton Bruckner. It was an unfortunate accident that the most balanced composition of the Seventh Symphony of Bruckner was the goodbye to the concert life of Schuricht in the Netherlands. A very good recording is released by MMS (Musical Masterpiece Society). MMS released most of the charcateristic recordings of Schuricht.
Schurlicht was an old student of Humperdinck and Reger.
He had a preference for late romantic German music.
During his stay in the Netherlands, as a conductor of the Utrecht state Orchestra
(of which van Otterloo was the second conductor), as a conductor at the Het(=Haag) Residentie orchestra during the Kurhaus summer concerts before the World War II, and later as a conductor at the Concertgebouw orchestra accidentally, he developed a broad spectrum
from the French and the Dutch masterpieces.
His introvert chararcter, which sometimes was changed into a fire, was quite in harmony
with the Dutch way of music performance. The Bruckner cycle were very well known even
outside the Netherlands, unfortunately this reputation gone with the death of Schuricht.
English translation by Dr. Jaap Beijersbergen.
86歳という高齢のシューリヒトの死によって、たぐい稀な指揮者が失われてしまったことになる。
ここ数年というもの、ステージへの登場はとても危なっかしいものだったが、いったん指揮棒を振り上げるや、周囲の雰囲気をことごとく高みへと引き上げてくれたものだ。その頂点に彼はいたに違いない。アントン・ブルックナーの交響曲ではいつもそうだった。最高に調和のとれたブルックナーの交響曲第7番が、オランダにおける彼の演奏活動の最後になってしまったのは、本当に残念なことだ。すばらしい録音がMMSからリリースされている。シューリヒトらしい録音のほとんどがMMSからリリースされている。
シューリヒトは、フンパーディンクとレーガーの古い弟子だ。彼は元来ドイツ後期ロマン派音楽を好んでいた。しかしオランダで活動する間に、つまり第2次大戦前にクアハウスにおける夏の音楽祭でハーグレジデンティ管弦楽団を指揮し、やがてコンセルトヘボウ管弦楽団をたまたま指揮する機会を持つ間に、フランスやオランダの名作などに幅広く親しむことになった。
はにかみ屋でありながら、時に燃え上がる彼の性格は、オランダ人にとても好感を与えるものだった。彼のブルックナーチクルスはオランダ国外にまで知られており、その名声はシューリヒトの死とともに失われてしまったのだ。(翻訳:小林 徹)
ウィレム・ヴァン・オッテルロー(Willem van Otterloo 指揮者)

もうすでに大分以前のことになりますが、私は偉大な芸術家、カール・シューリヒトの知遇を得、 彼と仕事をしたことがありました。1937年ユトレヒトで、アンリ・ヴァン・グーデバーの後を受けて、 私がオーケストラの正指揮者となったのですが、何分にも私はまだ若く未経験で沢山の演奏予定をこなす重荷に耐えきれませんでした。幸いにも、カール・シューリヒトがその中の相当数を引き受けて くれたのです。こうした関係が2年間続いて、私は多くのことを彼から教わりました。指揮上のテクニック、様式のつかみ方、オーケストラの動かし方、さらに音楽家達との人間関係についても、教えられるところが多く、私は厳密な意味では彼の弟子ではないのですが、彼の教室にはいたことになります。もちろん私達は、気質的にも異なるものを持っており、ちがう世代に属してもいたのですが、それにもかかわらず、シューリヒトの影響は、私の仕事の上に、いつも何らかの意味で力を示しているのです。例えば、そのあらわれの一つに、私をブルックナーに近づけたことがあります。今、私がブルックナーを非常に好んでいることをみても、私は彼に大きな恩恵をこうむっていることになるのです。
マルク・パンシェルル(Marc Pincherle 音楽学者)
カール・シューリヒト追悼のために、皆さんがその名声を賛える席に、是非私も参加させてください。
音楽家ならば誰でも、比類ない価値を持つ一人の指揮者が、彼と共に失われてしまったことを痛感しているでしょう。そして誠実で慎み深く、事大主義からは遠く離れたところで、ゆっくりと確信をもって花開いた彼の資質を賛え続けることでしょう。古典の偉大な伝統は、彼以上に優れた伝承者を持ち得ないことが、やがて明らかにされるその日まで。
私にとってこの卓抜な芸術家の死は、一人の大切な友人を失うことでもあるのです。1963年4月にミュンヘンで行なわれたレコード大賞(アカデミー・シャルル・クロから彼に贈られたA.C.C.ディスク大賞)の授賞式の際、私は彼に心から敬服して、その気持ちを伝えました。彼はそのたった数言の短い言葉にひどく感激して、以来お互いに好感を抱くようになり、そのすぐれた人間性にも接するようになったのです。繊細で寛大、情熱的で快いユーモアに富んだ彼は、その高齢や弱い体質にも拘わらず、いつも若々しい柔軟性、そして広い視野を持ち合わせていました。これを思うにつけても、彼が永久に私達のもとを去っていってしまった寂寥感を、どうすることもできないのです。
ヴィリ・ライヒ(Willi Reich)
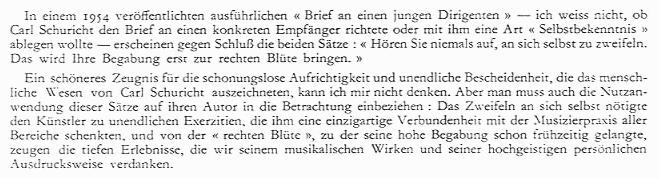
翻訳:山口 春樹氏
ハインツ・ワルベルグ(Heinz Wallberg 指揮者)
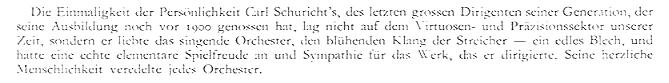
翻訳:山口 春樹氏
クロード・サミュエル(Claude Samuel 評論家) プロファイル
シャンゼリゼ劇場において、フランス国立オーケストラを指揮した、カール・シューリヒトの”英雄交響曲”
を聴いた、あの夜のことは、私の記憶にやきついて離れない。それまで、もう知り尽くされていたと
思われていたこのシンフォニーに、この晩、カール・シューリヒトがいきなり新しいしかも強烈な光を
投げかけたのだ。あらゆる無駄を切り捨て、しかも何にもまさる力をそなえたあの身振りでもって、、、。
この光は、神経の麻痺した音楽マニア達に、新たな感動を呼びおこしたのだ。自分達を揺り動かした
この同じ曲が、自分達の慣れ親しんだ筈の音楽の世界にずっと以前から存在したものであるのを
忘れかけていた彼らに。
この夜、劇場の舞台裏で、彼を祝福する友人達に囲まれて、既に80才を過ぎていながら幸せに顔を
輝かせていたカール・シューリヒトの姿が、今も目に浮かぶ。
アンリ・ゾーゲ(Henri Sauguet 作曲家)
カール・シューリヒトを喪なったことは、その高貴に輝く人格を失って、我々の芸術と我々の時代を
それだけ貧しいものにしてしまったことになる。この人の偉大な模範的な生涯は、完全な胸おどる美の中に偉大な作品の命脈を保とうと、自己のすべてを捧げる芸術家だけが辿りつくことのできる、高い頂の一つとして、いつまでも残っていることだろう。(「フランセ・ムジカ」所載)
ロジェ・ヴァンサン (Roger Vincent)
ミュンヘンでのA.C.C.ディスク大賞授与式で私は初めてカール・シューリヒトに会った。
この人格者―そして同時に指揮者―に会って、私は数多くのレコードの中から、彼のブラームスの
交響曲第4番だけが、なぜ特に絶賛を浴び、受賞の栄誉に輝いたかを理解することが出来た。
一たびオーケストラの前に立つや、この音楽家の日常生活にみられる老人の影が姿を消し、その若々しさと信念が、すべてを変えてしまうのだ。1965年に再び受賞したブルックナーの交響曲第7番にもみられるこの若々しさと信念は、それが生み出した音楽、そしてその音楽を忠実に再現したレコードと同様、不滅のものなのだ。アカデミー・シャルル・クロは、その受賞者名簿に、カール・シューリヒトの名を3度記入して、≪最もすぐれた人≫をえりすぐるというその責務を成し遂げたのである。

Rene Dumesnil
Carl Schuricht était pour moi, depuis bien des année, un ami très cher. Je lui dois beaucoup : les entretiens tenus avec lui chaque fois qu'il venait à Paris ou que je le retrouvais en quelque festival, m'ont enrichi. Assister à une répétition qu'il dirigeait était une leçon de technique et tout autant un exemple de conscience profesionnelle. je le reverrai toujours montant au pupitre pour conduire un orchestre illustre et s'adressant aux musiciens pour leur tenir à peu près ce langage : "Bien évidemment, messeiurs, vous connaissez par cœur l'œuvre que vous allez interpréter, et c'est bien ce qui m'effraie. Nous allons, si vous le voulez, la traiter comme s'il s'agissait d'une nouveauté dont l'encre est encore fraiche. Nous allons oublier tout ce que les traditions, la routine, ont pu faire de cette musique et ne demander qu'à elle-même, par le respect de sa structure, des idées qu'elle développe, de nous révéler ce qu'elle est" Eh bien, il ne lui fallut pas longtemps pour convaincre ces musiciens de l'excellence de ses vues. Il s'agissait là d'une restauration, quelque chose d'analogue à un nettoyage méticuleux, tel par exemple que le "ravalement" d'une façade empoussiérée.
L'homme était merveilleux. Je conserve de lui des lettres que je relis pour y retrouver la délicatesse de son amitié et la générosité de ses jugements.
Bernard Gavoty
Je connaissais Carl Schuricht. C'est dire que l'ayant applaudi maintes fois sur l'estrade, j'ai eu en outre le privilège de le rencontrer dans l'intimité.